故障の種類 |
目地材に関する項目 |
保護コンクリートに関する項目 |
目地材の飛び出し |
突きつけ部の隙間 |
目地材の破損 |
ひび割れ、欠け |
立ち上がり部の損傷 |
現象 |
 |
 |
 |
 |
 |
設計 |
対策 |
- 寸法安定性に優れた製品を使用する。
- 「公共建築協会評価品」 「成形伸縮目地工業会認定品」

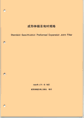
> 拡大
|
- 交差部には固定用部材を使用する。
- 収縮率0.5%以内でキャップ部に変形がない製品が良い。
- 成形伸縮目地工業会認定品の性能規格を満足する品質とする。
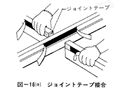
> 拡大
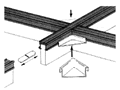
> 拡大
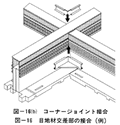
> 拡大
|
- 変形追従性に優れた製品を使用する。
- 「公共建築協会評価品」 「成形伸縮目地工業会認定品」
- 目地間隔は、3m以下とする。
- 断熱工法では2~2.5mの目地間隔とする事が重要。
- 断熱工法ではキャップ幅25mm以上の目地材を採用する。
- 車両が通行する場合はキャップ幅25mm以上の目地材を採用する。
> 詳細 |
- 目地間隔は、タテ・ヨコ3m前後とする。断熱工法では2.5m以下に設定する。
- 溶接金網を入れる。
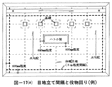
> 拡大
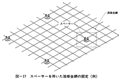
> 拡大
|
- 立ち上がり部に圧力を与えないように、厚さ5mm以上の入り隅緩衝材を取り付ける。
- 立上りより300mm~600mm離れた位置にボーダー目地を設置する。
- 保護コンクリートの下面まで達するように目地を切る。
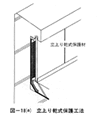
> 拡大
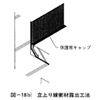
> 拡大
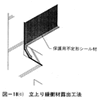
> 拡大
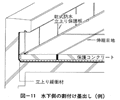
> 拡大
|
材料 |
対策 |
- アンカータイプまたは付着タイプの目地材を使用する。
成形伸縮目地材規格「形状による区分」
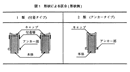
> 拡大
|
- 目地材は、下記のものを使用する。
- 「公共建築協会評価品」 「成形伸縮目地工業会認定品」
成形伸縮目地評価内容資料抜粋
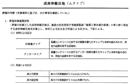
> 拡大
|
- 断熱材の上に設置する場合、据え付けモルタルを使用しないタイプの目地材を採用する方法もある。
断熱材の上に据付けモルタルなしで施工する固定工法
(例)
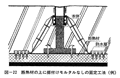
> 拡大
|
施工 |
対策 |
- 目地材相互の接合部には、ジョイントテープや目地材相互を固定する部材を使用する。
- 付着層の養生紙を取り除いてから、コンクリートに打設する。
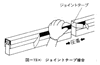
> 拡大
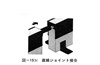
> 拡大
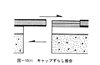
> 拡大
|
- 付着層の養生紙を取り除いてから、コンクリートに打設する。
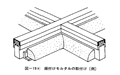
> 拡大
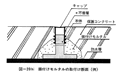
> 拡大
|
- 目地間隔は3m以下とする。
- コンクリート打設時に目地材がズレたり、倒れたりしないように養生する。
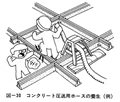
> 拡大
|
- キャップ幅は20mm以上のものを採用する。
- 標準施工マニュアルの注意事項に準拠する。
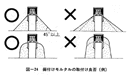
> 拡大
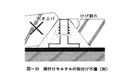
> 拡大
|

> 拡大
|
使
用
者
の
維
持
保
全 |
対策 |
「維持保全」のポイントは、
- 設計者から出された維持保全計画に基づく短期及び中長期の保全の実施計画の立案
- 保全計画を実施するための費用分担を含む資金計画の立案
- 保全計画の対象は屋根面のドレン・排水溝・パラペットの笠木・保護コンクリート等
- 清掃はドレン周り・排水溝の清掃及び植物の除去
- 周期は清掃を半年に一回、保守は二年に一回以上とする
:出典
「建築防水の耐久性向上技術」 建設大臣官房技術調査室 監修より |
- 目地材キャップにゴンドラの車輪などの重量がかからないようにする。
- 後工事で目地材を傷付けないようにする。
|
|
|